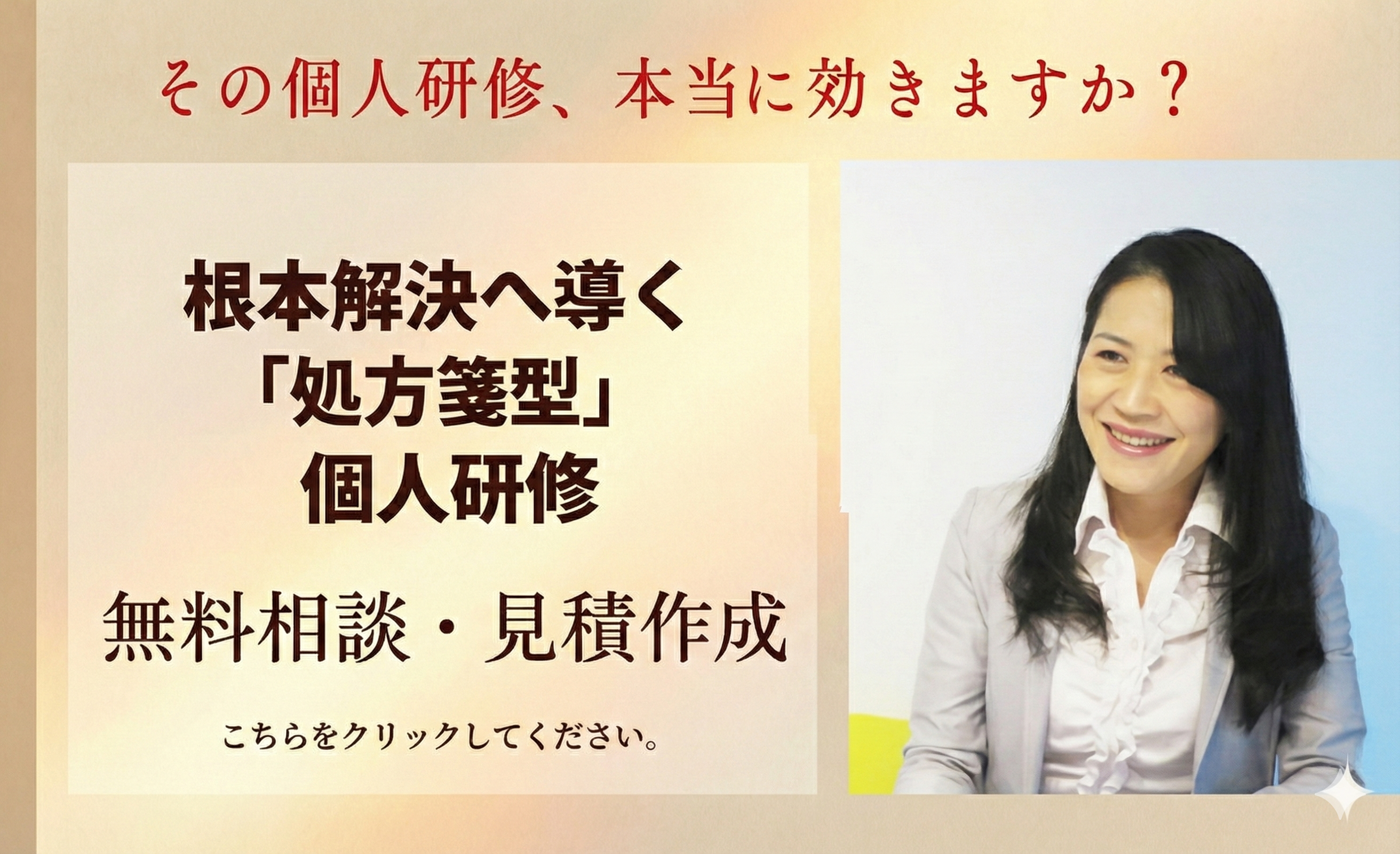ハラスメント加害者更生 行為者個人研修 講師紹介
今回はハラスメントの行為者個人研修、自己変革コーチングを担当しております講師をご紹介いたします。弊社で行っておりますセクハラやパワハラの行為者になられた方および、行為者ではないが個人として予防的に適切な指導法を学びたいという意思をお持ちの方に行う「自己変革コーチング」の講師です。全員がカウンセラーでもあり、様々な組織での勤務経験も豊富な講師です。
ハラスメント行為者個人研修 担当講師紹介
大美賀 直子
資格 公認心理師、精神保健福祉士、産業カウンセラー
経験:2009年より株式会社ハートセラピーに在籍し、企業、大学、医療機関でのカウンセリング・コーチング経験、企業研修の実務経験15年以上。受講者の目線に立ったわかりやすい研修が好評を呼び、リピート多数。その他、総合情報サイト「All About」でストレスのガイドを20年以上務め、著書・監修書の出版も多数。パワハラ、セクハラどちらの個人研修も得意。

個人研修をするにあたり心がけていること
個人研修を受けられる方は、表面的には反省の意を示していても、心の中では「自分だけが悪いわけではないのに、なぜ個人研修を受けなければならないのか!」という怒りを抱いていることが少なくありません。
私の個人研修では、そうした受講者の本音を真っ向から受け止めながら、ハラスメント再発防止に努めるだけでなく、周囲に信頼されるコミュニケーションをとれる人物になっていただけるよう、心理学理論やコーチング技法を駆使して指導しています。
個人研修は、受講者の一人ひとりが自らの人間性を成長させていく大切な時間です。正論を押し付けるだけでは、人の心は変わりません。私の研修では、講師の私自身が受講者に真摯に向き合い、人と人とのかかわりにおいて大切なことを真剣に、わかりやすい言葉で伝えていくことで、受講者が自発的にコミュニケーションを改善していける人物になれるように支援していきます。
ありがたいことに、研修の最後にはほとんどの受講者のみなさまから「個人研修を受講できて本当によかった」「今後は、周りから信頼されるようなコミュニケーションを自発的に行っていきます」といった感想をいただいております。
ケース1:「信頼できる!」と言われる人物に生まれ変わる「セクハラ行為者個人研修」
私の得意分野のひとつ、「セクハラ行為者個人研修」では、セクハラをしてしまった行為者がセクハラ再発防止を徹底するのはもちろん、「自ら率先して模範的なコミュニケーションをとる人物に変わる」ことを目標に研修を進めています。セクハラ行為者は、本質的に「コミュニケーション下手」であることが少なくありません。そのため、大人として周囲の人に信頼される適切なかかわり方の引き出しが少なく、酔った勢いやその場の雰囲気に任せて、セクハラ的な会話、行動をしてコミュニケートしようとしてしまうのです。
個人研修では、そうした行為者が自分の心理とじっくり向き合いながら、どのような話かけをすれば、周囲の人との信頼関係を築けるのかを納得できるまで説明し、実践できるように指導します。
セクハラ行為者の多くは、一度失ってしまった名誉を挽回し、もう一度、周囲の人とよい関係を築きたいと心から願っています。その願いを達成し、「○○さんなら信頼できる」「○○さんだからこそ相談したい」と言われる人物になれるように指導しております。そのため、研修が終わる頃には、みなさん晴れやかな笑顔で退室し、心新たに頑張っていくという意志を表明されます。受講者のみなさまのこうした表情を拝見すると、講師の私もたいへん励まされます。
ケース2:発想豊かなポジティブ上司に生まれ変わる「パワハラ行為者個人研修」
個人研修でお会いするパワハラ行為者の多くは、そもそも考え方が批判的であり、物事を何かと堅苦しく、ネガティブに考えてしまいます。そのため、本人には部下を追い詰めるつもりはないのに、「頭ごなしに否定された」「雰囲気が怖くて相談することすらできなかった」などと言われ、パワハラ行為者と見なされてしまうケースが多いのです。
こうした受講者に対し、私はこれまでの人生の中で、どうして批判的な思考が身についてしまったのかをとことん分析し、批判的思考のクセを改め、物事をポジティブに捉え直して、豊かな発想を導き出すトレーニングを行っています。
パワハラ行為者は、仕事を器用に進められない部下を見ると、以前なら「こいつは、なんで仕事ができないんだ!」とイライラしていたのかもしれません。しかし、私の個人研修を継続的に受けていただくと、「この部下のどこをサポートすれば、成長できるようになるかな?」と豊かな発想で考えられるようになっていきます。
個人研修では、まずは受講者様の思いをじっくり聞きながら、数々の心理学、カウンセリング、コーチングの理論とテクニックを組み合わせ、本人が納得して研修に臨めるよう、個人個人にフィットしたコンテンツをオーダーメイドで提供しています。ぜひ、パワハラ傾向のある方に受講をおすすめいただければと思います。
杉山修
資格:一般社団法人日本産業カウンセラー協会 産業カウンセラー
国家資格キャリアコンサルタント・2級キャリアコンサルティング技能士
経験:製造業(大手電機メーカー)にて30年以上勤務、管理職として部下100人をマネジメントした経験もある

ハラスメント個人研修をするにあたり心がけていること
「人は、気づいた瞬間に変わることができる」
これが私の研修の根底にある考え方です。個人研修では、行為者を責めるのではなく、その背景にある思いや状況を丁寧にひも解くことを大切にしています。
なぜその言動が生まれたのか?
その背後にある心理や環境を理解することで、相手を責めることなく、行動を見つめ直すきっかけが生まれます。
そして、「自分が本当に得たい結果を得るには、どんな言葉や態度、表情、行動が必要なのか?」に気づいてもらうことで、受講者自身が納得とともに変化を始めていきます。一方的な指導ではなく、内省と対話による深い学びと気づき。個人の行動変容を促していきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ケース1:個別研修を通じて解決志向の実践者へ
ある受講者は、部下に対して「死ね」と発言するなど、人格を否定する深刻なハラスメント行為に至っていました。初回面談でその背景を丁寧にたどると、上司からの強いプレッシャーにより精神的に追い込まれていた状況が明らかになりました。
研修では、問題の原因を追及するのではなく、未来に向けた小さな一歩を大切にする「解決志向アプローチ」を取り入れました。受講者はその考え方に強く関心を持ち、職場での実践を始めました。すると、部下との関係性に少しずつ変化が現れ、自分自身の感情の扱い方にも変化を感じられるように。
研修の終盤には「もっと学びたい」と自ら学習意欲を示すまでに変わり、以前とは別人のように穏やかな表情になっていました。
人は本来、誰かを傷つけたいわけではありません。そこには必ず理由があり、その背景に気づくこと。そして、解決志向のスキルを学ぶことで、人は自ら変わる力を取り戻していくのです。
ケース2:「得たい結果」から関わり方を見直す
ある受講者は、部下のミスや反抗的な態度に対してすぐに怒りの感情をぶつけてしまう方でした。その背景には、自身が若手時代に厳しい叱責を受けながら育ち、当時の経験が今の自分をつくったという信念がありました。「怒ることで人は育つ」と無意識に思い込んでいたのです。
研修では、「あなたが本当に得たい結果は何ですか?」という問いを繰り返しました。部下に責任を果たしてほしい、指示通りに動いてほしいという一方的な要求ばかりが並びます。しかし、「そのやり方で望む結果は得られましたか?」という問いに、受講者は「得られていない」と自ら答えました。
そこで、言葉づかいや態度、表情、そして相手の理解度に合わせた伝え方の重要性を伝えました。「部下に変われ」ではなく「自分がどう関わるか」が問われるのだと気づいたとき、表情が変わりました。
研修後は、「得たい結果」を常に意識し、「自分は今、どんな関わり方をしているか?」と自問自答する姿勢へと変化。立場が上がってもなお、自ら成長し続けようとする姿勢こそ、信頼される上司の姿だと感じさせる事例です。
柳原里枝子
資格:公認心理師、経営学修士(MBA)、産業カウンセラー、看護師、ハラスメントコンサルタント、第1種衛生管理者、人権啓発上級アドバイザー、ゲートキーパー、認定心理師等
経験:人事院「公務職場におけるパワーハラスメント防止対策検討会委員」、総務省消防庁「パワーハラスメント防止対策検討会委員」、厚生労働省「ハラスメント対策企画委員」、 内閣府 「政治分野におけるハラスメント防止研修教材等の作成に関する検討会委員」などに就任。元看護師として13年間病院や製造業健康管理室勤務、2008年に株式会社ハートセラピーを設立した。

ハラスメント個人研修をするにあたり心がけていること
講師は教えるのではなく、支援者であることが大切と考えております。受講者とは対等な関係性をもつことで、受講者が意見を言いやすい本音で語りやすいような場を作るようにします。
私がお会いした方々は悪意をもち加害者になったのではなく、育った環境や価値観へのこだわりの強さなどの影響を受けてパワハラ行為となっていたという方々です。ですからその方の人間性が悪いのではなく、個人研修にてハラスメントについて理解していただき、日ごろのご自身の行動や発言を見直し、改める部分に気づけば4回の研修で大きく変化します。
受講者が日ごろ困っていたことなども伺いコーチングやティーチングを織り交ぜ、必要な時はカウンセリング要素も入れて対応しています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ケース1:セクハラ加害者として懲戒処分を受けた管理者の例
社内の方に対してセクハラをしたと処分された方です。遠方のためすべてオンラインで3回ほど行いました。もともとセクハラ被害者と申し立てた方に対して、行為者としては「コミュニケーションが苦手そうだから」と思い、下ネタならコミュニケーションもはかどるだろうという理由で下ネタを発言。その後は、飲み会の席でボディータッチなどをしたとのことでした。
まずは、みんなが下ネタなら盛り上がるという思い込み、この人とは信頼関係があるから大丈夫という思い込みをなくすこと。被害者心理を理解していただく説明(断りづらい、恐怖心をいだいてこちらと会うのもつらくなることなど)をいたしました。セクハラの社内研修はイーラーニングで受けたそうですが、理解していないこともわかりましたので、基本的な事項も初回に伝えました。
同時に、被害者の方が社内に「○○さんにセクハラされた」と一斉メールで流してしまい、行為者自身が深く傷ついておりましたので、カウンセリング要素も取り入れて対応、反省は必要だがただ落ち込んで終わるのではなく、前向きに信頼を取り戻せるように周囲と関わることも計画にいれました。
取り返しのつかないことをしたのですから、自分自身も傷つくことは仕方がないと思いますが、真に反省をしていただき前向きに成長していただくことが大切です。加害者が体調を崩すことも割と多いので個人研修では体調も確認しながら進めています。
ケース2:パワハラをしたと指摘されたが個人研修でマネジメント力がかなり上がったケース
ご自身の価値観から外れたことをメンバーが行ったために注意したが、言い返されたためカッとなり余計な人権侵害ワードを伝えてしまった方です。日ごろから怒りなどが口にせずとも表情や態度に出てしまう傾向もあり、今回を機に個人研修を受けることになりました。組織からは今後管理職として活躍していただきたいためヒューマンスキルも学んでほしいという依頼でした。
パワハラという処分までされなくても、このように予防的に行為者個人研修を受講させる組織も多いです。いわゆる「安全配慮義務」ですね。
受講者は責任感が高く、仕事に対する信念も強く、素晴らしいのですが、自分の考えを通すにあたり周囲への圧が高かったり、相手が自分の価値観から外れたことをしていると厳しく言わずにはいられないという傾向がありました。個人研修では普段どのように部下とやり取りをしているか伺い、講師から率直にその伝え方は相手が○○のようにとらえてしまう可能性があることや、ボディーランゲージも注意する必要があることなど、実際の場面を振り返りながら双方向のコミュニケーションや価値観に対する許容範囲の広げ方などを伝えました。
問題志向で相手の足りないところに目が向いてしまうので、資源を活かす「解決志向」での指導法や関わり方を伝えると、2回目の研修までには毎日のように「承認行動」を部下たちに対して実践されておりました。(例えば自席の隣に空の椅子を置いておき、部下が報告に来た際には座ってもらい話を聞くなど)こうした行動が見えるくらいに実践することで周囲も変化していきます。今回の受講者も3回目にお会いした際は「他の部署の方から『メンバーの笑顔が増えたね』と言われた、また自席の隣の椅子に自ら座る部下が増えた」と嬉しそうに語られ、「今までよりも部下の不満や意見を知ることができるようになった」と話されました。何か問題が生じた際も、相手を追い詰める言い方はせずに「どうしたらよいか考えよう」など解決志向で問いかけるようになられたとのことでした。おそらく、本人が持っていた資源が良い方向に伸びたのだと思います。
1回ごとの研修の間に3から4週間の期間を開けている理由はこのように学んだことを現場で実践していただくためです。実践することで身につきますし、仮にうまくいかなかったときは次の研修で講師と検討することができるため、受講者の引き出しが増えるのです。
また、講師と双方向の対話ができる個人研修は集合研修よりも、受講者にゆとりが生まれるのだろうと思います。
内山 民子
資格:公認心理師、精神保健福祉士、産業カウンセラー、キャリアコンサルタント、米国フォーカシングインスティテュート認定トレーナー
経験:外資系企業の人事部にて人材育成・採用業務に従事した後、行政機関、IT企業の社員相談室、EAP、精神科クリニック、大学相談室など、多様な領域でカウンセリングおよび研修に携わってきた経歴をもつ。
集団研修では、自然体で分かりやすい表現を心がけ、実務経験に基づく事例を用いて理解を深める構成を重視している。個人研修では、行為者・被害者双方の心理に丁寧に寄り添い、内面の気づきと行動変容を促すプロセスを大切にしている。
2023年に横浜から札幌へ転居。現在はオンラインを中心に、道内での対面研修にも対応している。
個人研修を行うにあたり心がけていること
ハラスメント行為者の個人研修では、受講者の方が抱える不安や戸惑い、怒り、「自分は本当に間違っていたのか」という揺れる気持ちに丁寧に耳を傾けることを大切にしています。
処分を受けた方は強い抵抗感や不本意さを抱えながら研修に臨まれることが多く、表面上は冷静でも、内側には深い傷つきや混乱を抱えている場合があります。
そのまま知識だけを伝えても行動変容にはつながらないため、まずは安心して本音を語れる場づくりを重視しています。
「なぜその言動に至ったのか」を一緒に振り返り、価値観や思い込み、コミュニケーションの癖、パーソナリティの特性に目を向けながら、再発防止に必要な視点を整理していきます。
エゴグラムやコミュニケーションチェック、解決志向アプローチ、アンコンシャスバイアス、リフレーミング、描画ワークなどを組み合わせ、内面の気づきと行動の選択肢を広げる“きっかけ”として活用しています。
また、受講者の心理状態に応じて、資料中心から対話中心へ切り替えるなど、その場で最適な進め方を柔軟に選択します。
怒りや防衛が強いときには無理に学びを押しつけず、まずは気持ちを受け止め、落ち着いた段階で改善の視点を取り入れます。
受講者の方が「変わらなければならない」ではなく、「こう変わっていきたい」と感じられるよう心がけています。
長年培ってきた価値観や指導スタイルを見直すことは、決して簡単ではありません。ときに痛みを伴う作業でもあります。しかし、そのプロセスを丁寧に支え、受講者の方が自分のペースで変化を積み重ねていけるよう寄り添うことが、個人研修の役割だと考えています。
ケース1:抵抗の強い行為者が、対話を通じて変化の入り口に立つまで
ある受講者の方は、研修開始時に「自分は間違っていない」「時代が変わっただけだ」と強い抵抗感を示し、怒りや不安、処分による落ち込みが入り混じった状態でした。研修そのものへの不信感も強く見られました。私は、その気持ちを否定せず、抱えている痛みや葛藤に丁寧に耳を傾けるところから研修を始めました。
パワハラの定義や背景を確認しながら、ご自身の言動が相手にどのように受け取られた可能性があるかを一緒に振り返ると、口調や表情など非言語的な影響に少しずつ気づかれるようになりました。当初は資料への拒否感や防衛的な姿勢が強くありましたが、対話を中心に進めることで徐々に心がほぐれていきました。
工夫している点を丁寧に拾いながら話を進めると、「できていることも共有したい」「良い点をほめたい」といった前向きな言葉が生まれ、指導時の口調を意識した結果、部下のミスが減るという具体的な変化も報告されました。
ケース2:パーソナリティ理解と解決志向による関係改善例
厳しい指導が続いた結果、部下との関係が悪化し、パワーハラスメントと受け取られた受講者の方。
研修では、エゴグラムやコミュニケーションチェックを用いてご自身の特性やコミュニケーションの癖を客観的に振り返っていただきました。その中で、「相手の受け取り方が自分の意図と異なることがある」という気づきが生まれ、これまでの指導がどのように伝わっていたのかを初めて深く考える機会となりました。
解決志向のアプローチを紹介すると強い関心を示され、「段階的な目標設定」「スモールステップ」の考え方を積極的に取り入れようとされました。「なぜできないのか」ではなく「どうすればできるようになるか」という視点で部下と関わる方法を一緒に検討した結果、指導の仕方が大きく変化しました。
研修の終盤には、「冗談に冗談で返してくれるようになった」「部下が以前ほど固まらなくなった」と具体的な変化を嬉しそうに語られました。これは、受講者の方が自ら伝え方を見直し、行動を変えた結果であると感じています。
私は、研修の中でこうした変化が生まれる瞬間に立ち会うたび、受講者の方が本来持っている力が再び動き出したことを実感します。
個人研修は、行為者を責める場ではなく、再び信頼を築き直すための第一歩を支える場でありたいと考えています。