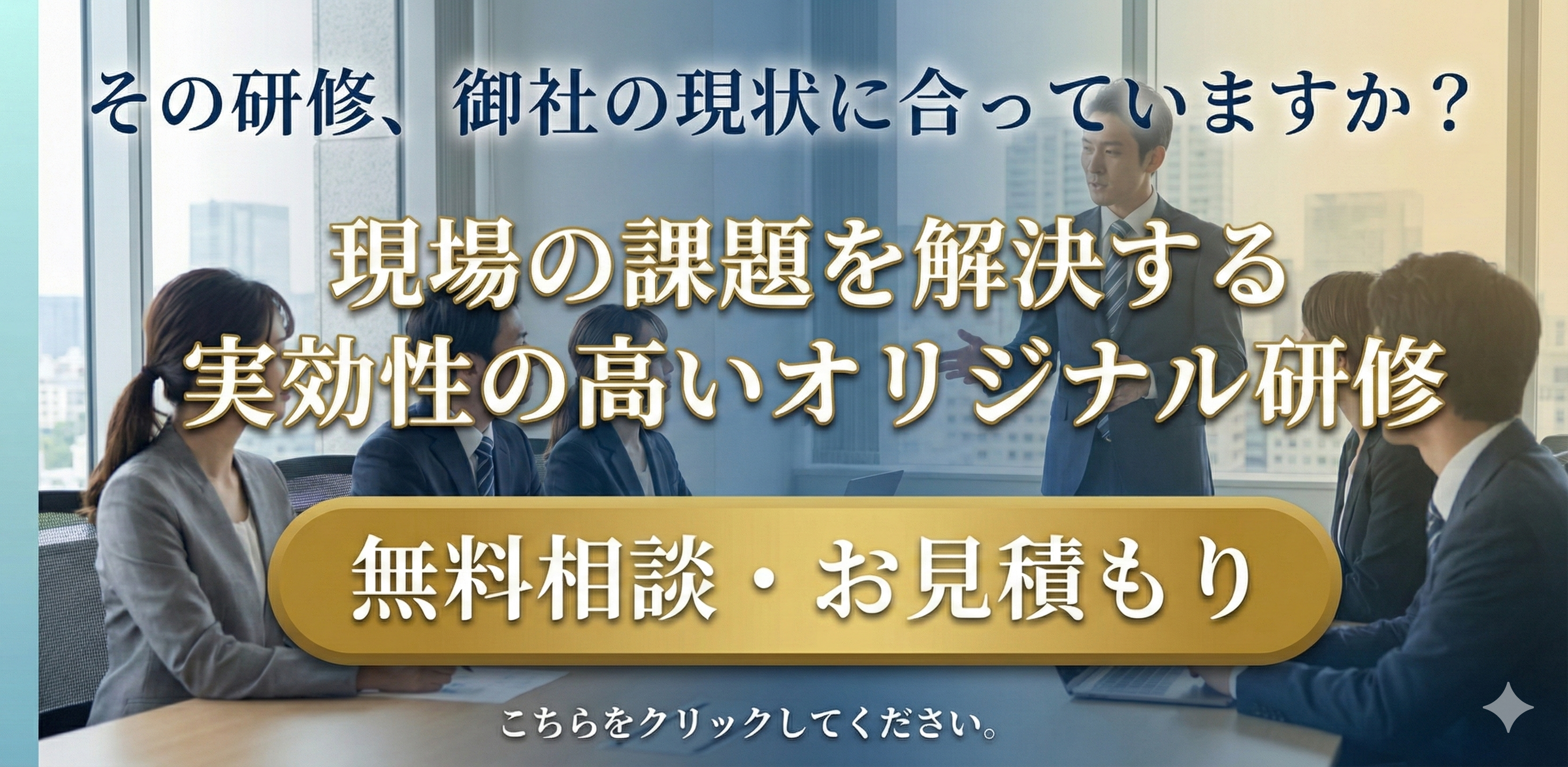製造業ハラスメント研修 製造現場ハラスメントの特徴と向き合い方
製造業の現場では、日々の業務が時間と品質に追われる中で、チームワークと緊張感が求められます。
こうした環境は、効率的な生産を支える一方で、ハラスメントが生じやすい土壌にもなり得ます。
特に、製造業特有の組織構造や文化が、ハラスメントの形を複雑にし、見えにくくしていることがあります。
ハートセラピーでは、職場環境に合わせたハラスメント研修をご提供しています。
忙しさや緊張感の中でも、安心して相談できる体制づくりを支援します。
組織の構造や文化に配慮した内容で、オンラインでも実施可能です。
目次
製造業特有のハラスメントの背景と特徴
製造業の現場での業務プレッシャーの高さ
製造業の現場では、納期厳守や品質管理の徹底が求められ、日々の業務に強いプレッシャーがかかっています。
こうした環境は、現場の責任感を高める一方で、ミスに対する叱責が過剰になりやすいという課題も抱えています。
特にライン作業では、一人のミスが全体の工程に影響を及ぼすため、感情的な言動が「指導」として正当化されてしまうケースも少なくありません。
また有害物質や危険な機械を使う作業などもあるため「安全を守る観点」からも厳しく指導しているという声を聞きます。
結果として、厳しい言葉や態度が日常化し、ハラスメントの温床となる可能性があるのです。

階層的な組織構造と「叩き上げ」文化
製造業の現場では、上下関係や「先輩・後輩」意識が強く根付いており、パワーハラスメントが温存されやすい土壌があります。
経験年数や役職によって発言力が偏り、若手社員や非正規社員が声を上げにくい状況が生まれがちです。
また、「叩き上げ」文化に基づく「見て覚えろ」「やって覚えろ」といった教育スタイルが根強く残る職場では、厳しい指導がハラスメントに発展しやすい傾向があります。
こうした構造の中では、パワーハラスメントが見過ごされやすく、精神的な負荷が蓄積されていくのです。
コミュニケーション環境の制約と無意識のハラスメント
製造業の現場では、騒音や時間的制約により、コミュニケーションが一方通行になりやすく、誤解や摩擦が生じやすい状況があります。
作業音が大きい環境では、「早くしろ!」「何度言ったらわかるんだ!」といった短く強い言葉が使われがちで、威圧的な印象を与え、無意識のハラスメントにつながることもあります。
また、危険作業において身体接触を伴う指導が必要な場面もあります。たとえば、体をつかむ、肩をたたくといった行為は、安全確保のためであっても、受け手によってはハラスメントと受け取られる可能性があります。
こうした場面では、事前の声かけや丁寧な説明が不可欠です。
さらに、休憩室・更衣室・喫煙所などの非公式な空間での雑談にも注意が必要です。こうした場では、セクハラ的な発言やいじめにつながる言動が無自覚に行われることがあり、職場の心理的安全性を損なう要因となります。
三交代勤務でいつも同じグループで仕事をしているという状況も多く、メンバーの人間関係が良くないとお互いに慢性的なストレス状態となり心のゆとりがなくなることでいさかいも起きやすくなります。

指導される側受け取る側の問題から生まれるハラスメント
指導される側も時代背景の変化により以前よりも叱られたり注意を受けるとパワハラと受け止めやすくなっています。学生時代など叱られたことがあまりなかったり、個性を大事に伸ばす丁寧な指導を受けてきている若者は現場で急に「見て覚えろ」「これやっとけ」という曖昧な指導を受けると戸惑い「指導をしてくれない」「教えてくれない」「無視されている」と感じます。きつい指導にも慣れていないため必要以上に落ち込んでしまう者も増えています。指導される側も「教えてくれるのが当たり前」という姿勢ではなく自ら積極的にコミュニケーションを取り質問していく行動が必要です。また、武道の受け身のように叱られたり批判された時の受け止め方を知っておくことは大変役立ちます。
製造現場むけハラスメント研修
では、こうした課題にどう向き合えばよいのでしょうか。
まず重要なのは、「指導」と「ハラスメント」の境界線を明確にすることです。厳しさが求められる場面でも、相手の尊厳を損なわない言葉遣いや態度が不可欠です。受ける側は注意を受けたら何でも「ハラスメントだ」と思わないことも大切です。正しい知識をもつことで適切な伝え方や受け止め方が出来るようになります。
そのためには、イーラーニングではなく集合研修の実施が効果的です。イーラーニングでは一人で聞くため自分の都合の良いようにフィルターをかけて聞いてしまい、他の人の意見も聞けないためハラスメントをしている方は特に気づきを得ません。
また、研修内容にも工夫が必要です。上記のような製造業特有のハラスメントの形態があるため、一般的な研修内容では現場の実感に結びつきにくいという課題もあります。そのため、製造現場特有の事例、要因、対処法などカスタマイズが不可欠です。
弊社は代表の柳原をはじめとして製造業出身者の講師が2名おります。また、カウンセラーとして製造現場で定期的にカウンセリングをしている講師もおります。よって現場にあう内容の研修をご提案しております。
対象者の優先順位ですが
ライン長や班長など、現場リーダー層を対象とした定期的な研修を通じて、ハラスメントの予防と早期発見を促すことが重要です。現場の空気を変えるには、まず管理者の意識改革から始める必要があります。
次いで、若手社員にも何でもハラスメントと受け取らないために「叱られた際の受け止め方」「適切な断り方や質問の仕方」「自分たちも加害者になりうる事例」「仮に被害者になってしまった時の対応」を学んでもらう必要があります。
ハラスメント対策研修はコミュニケーションについても学びますのでより良い組織づくり、お互いを活かす生産性の高い職場づくりにも寄与します。

製造業のハラスメント対策研修以外の取り組み
相談窓口の設置とその信頼性の確保も欠かせません。匿名での相談や第三者による対応など、安心して声を上げられる仕組みが必要です。
さらに、双方向のコミュニケーションを促す場づくりも有効です。1on1ミーティングや提案制度など、現場の声を拾い上げる仕組みが職場の風通しを良くし、ハラスメントの芽を摘むことにつながります。
世代間ギャップがある中での管理者は若手育成に苦慮していることも多いため、管理職へのフォローも必要です。
マネジメント研修・コミュニケーション研修を受講させるだけではなく、コーチングやカウンセリングを導入して管理者が部下指導する上で困っていることを相談できる場を提供しましょう。
パワハラの加害者たちは皆さん部下とのやり取りで困っています。ハラスメント加害者個人研修では講師が寄りそい「管理者の得たい結果を得る為にはどのように接していけば良いか」を考えていただいています。
現場の声に耳を傾け、互いを尊重し合う文化を育むこと。それこそが、これからの製造業に求められる姿勢ではないでしょうか。
弊社では、ハラスメント対策研修以外にも前向きな課題解決手法を学ぶ研修、アンガーマネジメント研修、コミュニケーション研修、メンタルヘルスレジリエンス研修、コーチングなど製造業に役立つ内容のサービスを提供しております。御社の社員がイキイキと働けるようにお手伝いをさせていただけると幸いです。下記バナーよりお気軽にお問い合わせください。代表の柳原がお話を伺います。
関連コラム