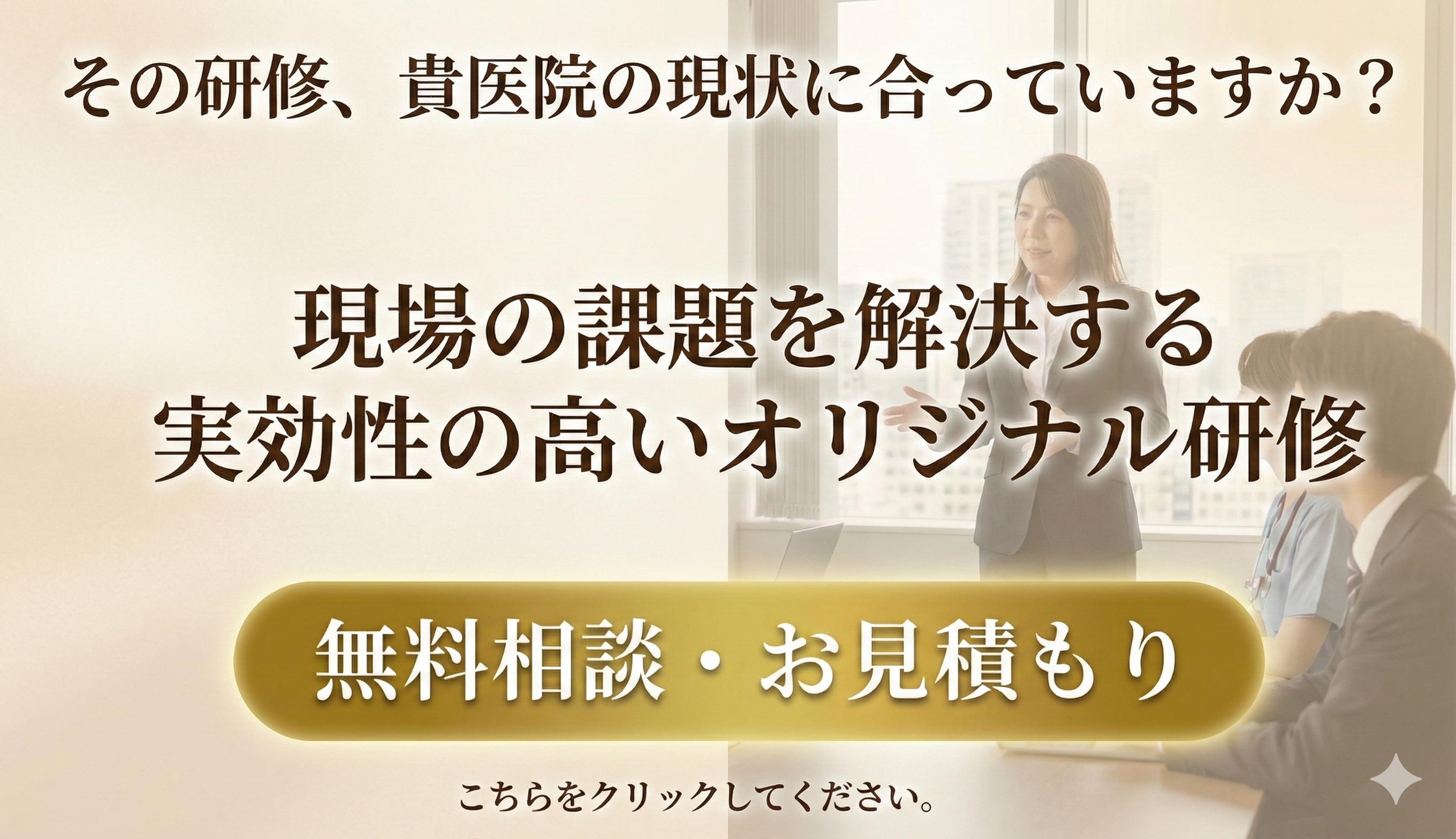医療現場に潜む“見えにくい”ハラスメント ―「厳しさ」の名のもとに見過ごされる痛み
「忙しいから仕方ない」「現場ではよくあること」――そんな言葉の陰で、誰かが静かに傷ついているかもしれません。
医療の現場では、命を守るという使命のもと、多くの職員が日々限界まで力を尽くしています。その中で、ふとした言葉や態度が、知らず知らずのうちに誰かの尊厳を損なってしまうことがあります。
医療機関におけるハラスメントは、特別な出来事ではなく、“日常の延長線上”で静かに起きているのです。
本コラムでは、こうした構造的な背景に目を向けながら、予防と改善に向けた視点を探っていきます。

目次
医療機関特有の緊張感と上下関係
命を預かる現場の緊張感
医療の現場は、命を預かるという特別な使命を背負っています。
そこには、常に張り詰めた空気と、迅速な判断が求められる緊張感が漂っています。患者の安全を守るために、厳格なルールや高い専門性が必要とされるのは当然のことしかし、その「厳しさ」が、時に人を傷つける言動を正当化してしまうことがあるー
そんな“見えにくい”ハラスメントが、医療機関には潜んでいます。
ヒエラルキー構造
医療現場には、職種間の明確な上下関係があります。
医師、看護師、技師、事務職など、それぞれの役割が異なる中で、発言権や裁量に大きな差が生まれやすい構造が存在します。
若手職員が「教育的指導」と称して人格を否定されるような言葉を浴びることも少なくありません。
こうした言動は、表面的には「指導」や「指摘」として扱われがちですが、受け手にとっては深い傷となり、心理的安全性を脅かします。
多忙によるコミュニケーション不足
医療機関での過密なスケジュールの中では、ちょっとした言葉の行き違いや認識のズレ、配慮の欠如等、感情的なすれ違いが蓄積していく可能性があります。
本来なら「ありがとう」と伝えたい場面で、「なんでこんなこともできないの?」という苛立ちが先に出てしまい、ハラスメントと受け取られることもあります。
医療現場ハラスメントが起きやすい構造的背景
閉鎖的な職場環境
医療機関は閉鎖的な職場環境になりやすく、外部との交流が限られているため、内部の力関係や慣習が固定化されやすい傾向があります。
「昔からこうだから」「医療現場は厳しくて当然」といった文化的な正当化が、ハラスメントの温床となり、職場の人間関係がさらに悪化することもあります。
患者・家族からの圧力
忘れてはならないのが、患者やその家族からの圧力です。医療従事者は、暴言や過度な要求にさらされることもあり、組織として守られていないと感じると、職員の心理的負担は倍増します。
こうした状況下で、ハラスメントの相談窓口が機能していない、あるいは報復を恐れて声を上げられないという現実も、問題を深刻化させています。

すぐにできる医療現場ハラスメント予防策
こうした構造的な背景を踏まえると、現場での“ちょっとした言葉”が、思いのほか大きな影響を与えていることに気づかされます。
ハラスメントの予防には、制度や研修といった仕組みも欠かせませんが、まずは日々のコミュニケーションを見直すことが、最も身近で確かな一歩になります。
今日から実践できる予防策をいくつかご紹介します。
今日からできる“言葉の見直し”
言い換えチャレンジ:「前にも言ったよね?」→「もう一度確認しましょうか」
安心を伝える一言:「いつでも聞いていいよ」「一緒に考えよう」
比較しない伝え方:「○○さんのやり方も参考になるけど、自分のペースで大丈夫ですよ」
1on1や日常会話で使える“予防の習慣”
「最近どう?」の声かけ習慣
→ 相手の変化に気づくきっかけに。業務外の話題も歓迎する空気づくり。
「言いづらいことも言っていいよ」の宣言
→ 上司・先輩からの一言が、心理的安全性を支える土台に。
「その言い方、ちょっと気になったんだけど…」の練習
→ 気づきを伝える対話の練習。

チームで取り組める“ミニアクション”
「NG言葉・言い換えリスト」をみんなで作る
→ 休憩室や共有フォルダに貼るだけでも、意識が変わります。
「ありがとう・ごめんね・助かった」の見える化
→ 感謝や謝罪を言葉にする習慣が、関係性の質を底上げします。
「この言い方、どう思う?」を話し合う時間をつくる
→ 5分でもOK。ケースをもとに対話する場が、予防の土壌になります。
医療の質を高めるためには、職員一人ひとりが安心して働ける環境が不可欠です。
ハラスメントの“見えにくさ”に目を向け、構造的な背景を理解することは、組織としての責任であり、患者の安全にも直結する課題です。
今こそ、「厳しさ」と「尊重」を両立させる職場づくりが求められています。
今回は医療現場で長年カウンセリングを行っている内山民子カウンセラーが執筆いたしました。
弊社は代表の柳原が元看護師であり、数名のカウンセラーが医療や福祉の現場で長年カウンセリングを行っておりますので、医療現場に即したハラスメントやメンタルヘルス対策を支援することができます。全国の病院や看護協会、医師会からの依頼で研修を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
最近話題のカスタマ―ハラスメント研修も医療機関むけにコンテンツございます。
関連コラム