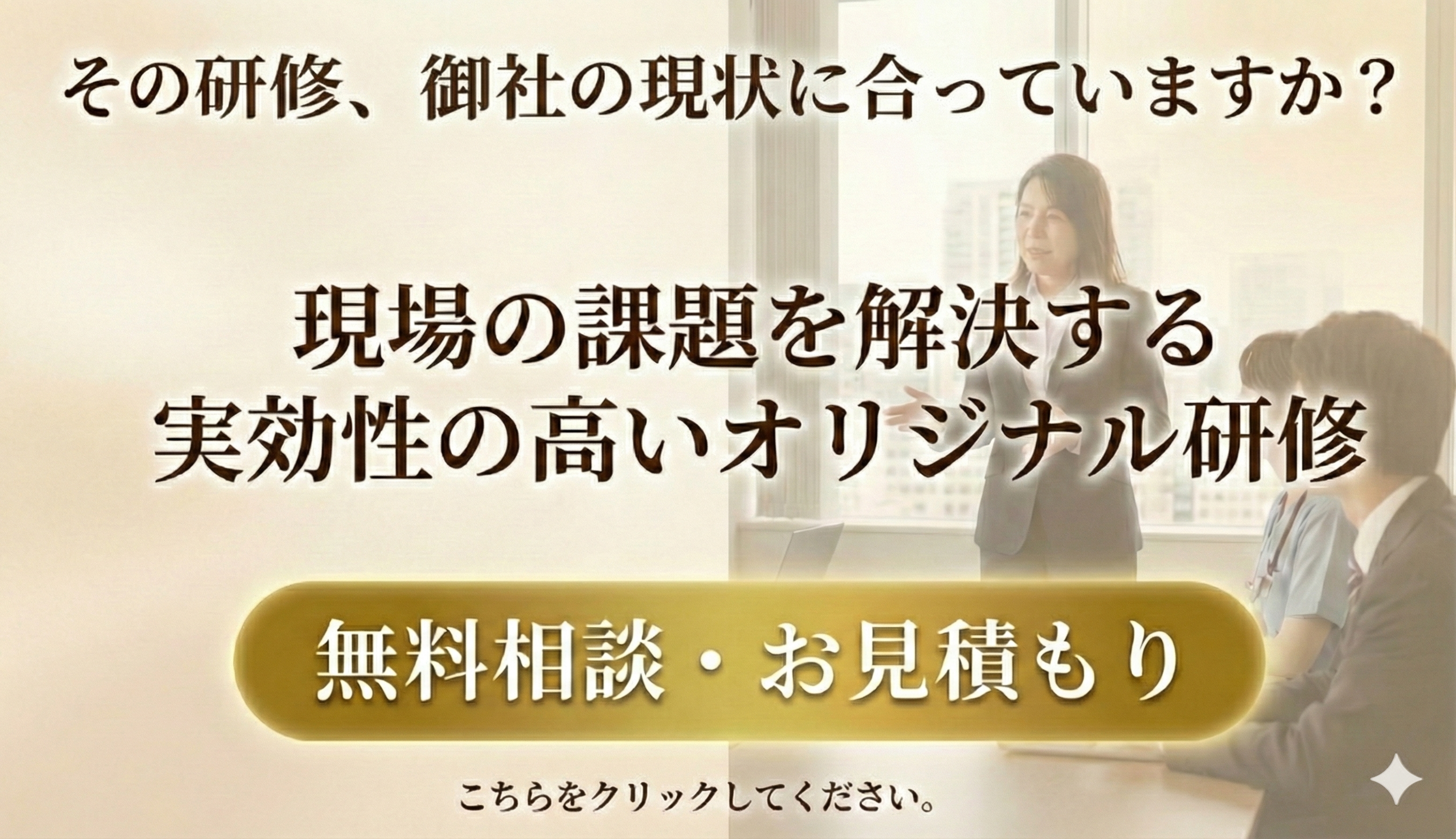ハラスメント相談対応の次に待つ“難所”──ハラスメント事実確認におけるヒアリングの壁
「ハラスメント相談対応よりも、ヒアリングのほうがずっと難しい」──ハラスメント対応に関わる現場で、何度も耳にしてきた言葉です。
ハラスメント相談対応では、まず「話を聴く」ことが中心になります。相手の気持ちに寄り添い、安心して話せる場をつくることが大切です。
しかし、ハラスメント事実確認(ヒアリング)に進むと、状況の把握、事実確認、関係者の感情や利害関係の整理など、より高度で繊細なスキルが求められます。
特にハラスメントのようなセンシティブな問題では、聞き方ひとつで信頼関係が揺らぎ、対応が逆効果になることもあります。
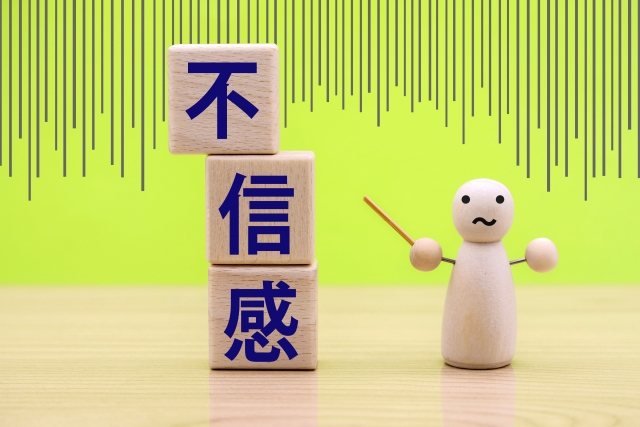
ヒアリングは、単なる情報収集ではなく、公正かつ迅速な解決に向けての対話です。
本コラムでは、実際に寄せられた事例をもとに、事実確認(ヒアリング)時に意識したい視点や工夫を整理してみたいと思います。
事例①:ハラスメント事実確認(ヒアリング)はしているのに、事実を具体的に把握していない
ハラスメント事実確認とは、感情を否定することなく、事実を明確にしていくこと
ある職場で、ハラスメント相談を受けた担当者が「本人から話は聞いた」と言っていました。
けれども、よく聞いてみると、「不快に感じた」「威圧的だった」「相手が私のことをけむたがっている」といった抽象的、主観的な言葉ばかり。日時、場所、具体的な言動は曖昧で、対応の根拠としては弱いものでした。
こうしたケースは少なくありません。
相談者の気持ちや思いを受け止めることは大切ですが、それだけでは“事実”にはなりません。
逆に、具体性を求めすぎて「証拠がないなら対応できない」と突き放してしまえば、信頼は失われます。
大切なのは、感情と事実を分けて考えること。そして、相談者の語る“体験”を丁寧に掘り下げながら、少しずつ具体性を積み上げていくことです。
例えば「相手が私のことをけむたがっている」と言われた場合は、「具体的にどのような相手の態度によりそのように感じたのですか」と事実を確認する必要があります。
事例②:ハラスメント相談者の話をすべて事実だと、前提して行為者事実確認(ヒアリング)を行っている
ハラスメント相談者に穏やかに寄り添いながら話を聞いている様子は、安心感を与えるものです。
けれど時に、その寄り添いが「相談者の語り=すべて事実」として扱われてしまうことがあります。
特に私の経験からするとセクハラ被害については組織側が相談者側の言い分に従いやすい傾向があります。
相談者の語りには、苦しみや怒り、混乱が含まれていることが多く、対応者としては自然と気持ちが相談者に傾くものです。
だからこそ、意識的に「今聞いているのは、あくまで相談者の一つの視点」と捉える姿勢が必要です。
行為者への事実確認(ヒアリング)の際に「なぜそんなことをしたのか」という決めつけた前提で始まると、対話は防御的になり、事実確認が困難になります。行為者に対しても、「あなたの話も大切に聞きたい」という中立的なスタンスを示すことで、双方の信頼を得ながら事実に近づくことができます。
共感は必要、でも、事実はまだ仮説。共感と中立性は、対立するものではなく、両立できるものです。
対応者がそのバランスを保つことで、組織全体の信頼が守られるのです。

事例③:ハラスメント相談者の話を相談対応者の無意識の偏見で否定している
「それはあなたの感じ方では?」と、相談者の感情や体験を軽視する対応。
「あの人はいつも文句ばかり」「またかと思ってしまう」──ハラスメント相談員の口ぶりから、相談者が職場で疎まれていることが伝わってくることがあります。実際に話してみると、確かに感情的で話が長く、対応が難しいと感じることもあります。
けれども、相談内容を丁寧に聞いていくと、「業務の進行を妨げるような言動を受けている」「特定の人からの繰り返しの干渉されている」など、放置すれば職場全体に影響するような問題が含まれていることも少なくありません。
こうしたケースでは、「人柄」と「訴えの中身」を切り分けて考えることが不可欠です。対応者が相談者の印象に引きずられてしまうと(無意識の偏見)本来対応すべき問題が見過ごされる危険があります。
ハラスメント相談対応においては、「誰が言っているか」ではなく、「何が起きているか」に焦点を当てる姿勢が求められます。面倒な人だからこそ、丁寧に対応することで、職場の信頼が守られるのです。
事例④:ハラスメントとされる言動の背景に、異動や人間関係の軋轢があるケース。
ある職場で、新任マネージャーが着任して間もなく、複数の部下から「威圧的な言動がある」との相談が寄せられました。
ヒアリングを進めると、確かに厳しい言葉や高圧的な態度が見受けられましたが、同時に「前任者は優しくて自由だった」「急に締め付けられて戸惑っている」といった声も多く聞かれました。
このようなケースでは、ハラスメントとされる言動の背景に、「人間関係の変化」や「期待とのギャップ」が存在していることがあります。新任者が悪意を持っているわけではなく、むしろ組織の方針に沿って業務改善を進めようとしていることもあるのです。
事実確認の際には、単に“言動”だけを見るのではなく、「その言動がどのような関係性の中で生まれたのか」「職場の空気や過去の経緯がどう影響しているのか」といった、文脈を読み解く視点が欠かせません。
そうすることで、個人を責めるのではなく、組織全体の課題として捉えることが可能になります。
事例⑤:組織が厳しい指導を求めて就任させた人がパワハラと言われたケース
「職場が緩んでいるので、厳しく立て直してほしい」──そう言われて着任したマネージャーが、数ヶ月後には「パワハラの加害者」として相談を受けることになった事例がありました。
本人は「組織の期待に応えようとしただけ」と語り、実際に業務改善の成果も出ていました。
しかし、部下たちは「言い方がきつい」「萎縮してしまう」と感じており、職場の空気は冷え込んでいました。
問題なのは、こうした状況に対して、組織が「本人の問題」として処理しようとしたことです。
ハラスメント対応は、個人の言動だけでなく、組織の方針や支援体制も問われるべきものです。
厳しい指導を求めるなら、その影響をどう支えるか。現場とのギャップが生じたとき、どう橋渡しするか。事実確認とは、こうした“構造的な責任”にも目を向けることが求められます。

「事実確認とは、“誰かを裁く”のではなく、“組織を守る”ための営み
ハラスメント対応における事実確認は、単なる情報収集ではありません。それは、組織の信頼を守るための対話であり、関係性を再構築するための第一歩です。
対応者が相談者に共感することは、安心感を与えるうえで欠かせません。しかし、その共感が「語り=事実」という前提にすり替わってしまえば、行為者との信頼は失われ、職場の分断を招くことになります。加害者と言われた方から組織が訴えられる可能性もあります。
逆に、相談者の人柄や話し方に引きずられて「面倒な人だから」と訴えを軽視すれば、対応の公平性は損なわれ二次被害が広がります。
事実確認とは、「何が起きているか」まさに事実に向き合う営みです。
そこには、感情・関係性・組織の力学といった、見えにくい要素が絡んでいます。だからこそ、対応者には“共感”と“中立性”の両立が求められます。
難しいケースこそ、丁寧に耳を傾け、背景を読み解き、構造的な責任に目を向けることが必要です。
それは、誰かを裁くためではなく、組織全体が安心して働ける環境を取り戻すための営みなのです。 公認心理師 内山民子著
最後までご覧いただきありがとうございました。株式会社ハートセラピーでは「ハラスメント相談対応研修」「ハラスメント事実確認(ヒアリング)研修」をオンラインにて開催しております。詳細は下記をクリックしてください。また、お客様の組織に全国出張して研修もいたしますのでお気軽にお問い合わせください。