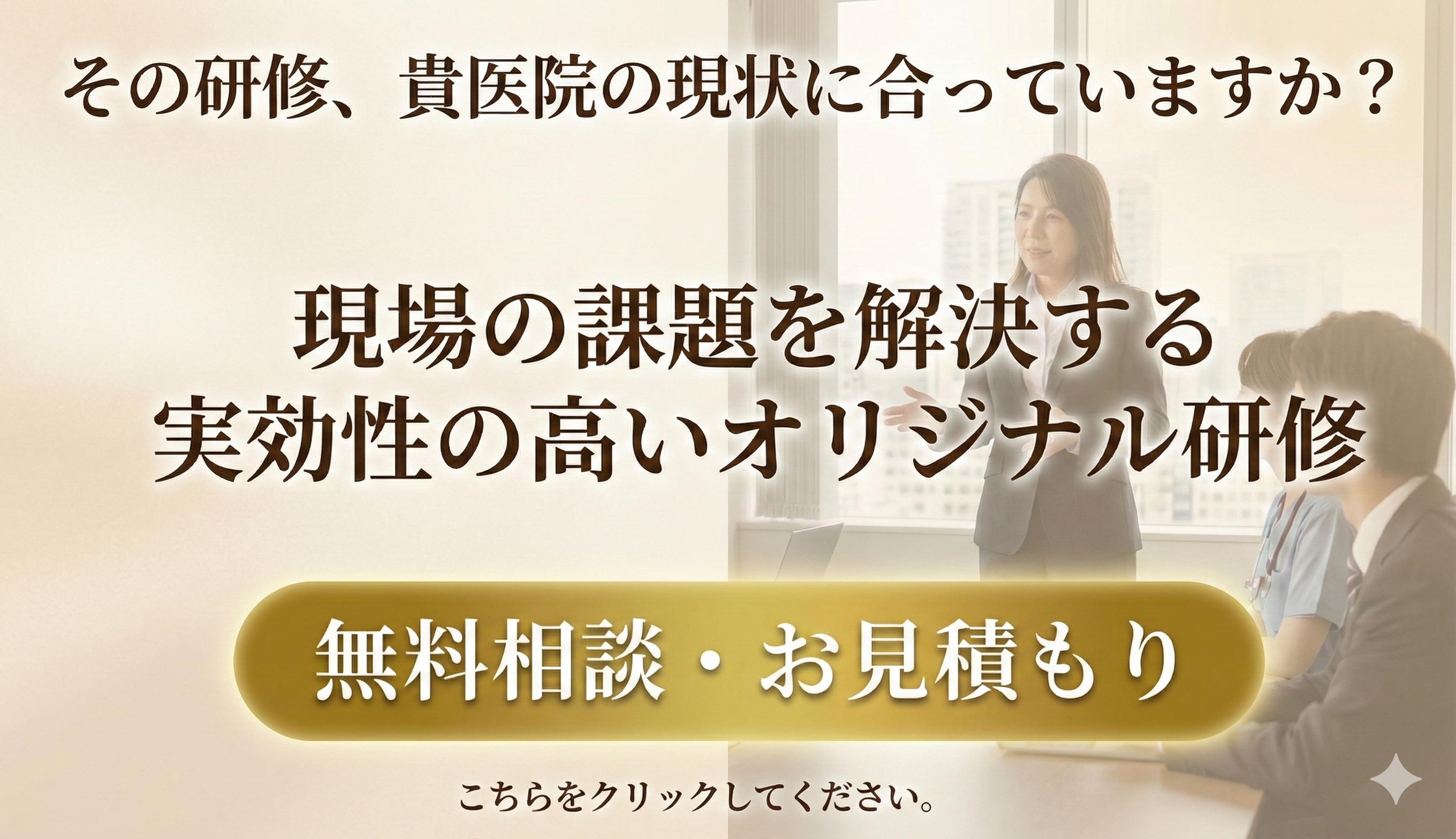コラム
コラム
看護師のパワーハラスメント対策(看護師パワハラ実態と対策方法)【看護師・公認心理師執筆】
看護の現場は、患者さんの命と健康を守るという崇高な使命感に支えられています。しかし、その裏側で深刻な問題となっているのが、パワーハラスメント(以下、パワハラ)の存在です。多忙でストレスの多い環境は、残念ながらパワハラが発生しやすい土壌を作り出しており、多くの看護師が心身ともに疲弊し、離職を余儀なくされています。
このコラムでは、看護師が直面するパワハラの実態と、個人として、そしてチームとしてできる対策について解説します。
目次
看護現場におけるパワハラの実態
日本医療労働組合連合会の調査からも明らかなように、看護師のパワハラ加害者は上司や医師、同僚と多岐にわたります。特に、閉鎖的なチーム医療の環境下では、以下のような行為が横行しやすい傾向にあります。
パワハラを行った相手として最も多いのは以下の通りです。
- 看護部門の上司: 60.1%
- 医師: 39.9%
- 同僚: 21.4%

パワハラの内容は以下の通りです。
- 精神的攻撃: 人前での叱責、人格否定、「使えない」といった暴言
- 人間関係からの切り離し: 意図的な情報共有の遮断、無視
- 過大な要求: 達成不可能な業務量の押し付け
| 上司からの威圧的な言動と態度 | 同僚・先輩からの威圧的な言動と態度 |
|
・高圧的な言葉で否定する。無視する。話を聞かない。 ・理不尽に怒られる。 ・同期との差別、ミスしたことを何年も言われる。 ・必要以上に強い口調で、感情的な態度、質問攻めにされる。 ・休みや年休・生理休暇を希望したら嫌味を言われ、取らせてもらえない。 ・超勤していても無視をされ、超勤申請をしてもダメと言われる。 ・人格否定、看護師のプライドを否定、会議や委員会の仕事などの強制。 ・異動や退職を勧められる、迫られる。 ・男性だからとクレームの多い患者の対応を振られる。 |
・高圧的な言葉で話しかけてくる。 ・意見を頭ごなしに否定する。 ・適切な指導もしない状態で、能力が低いと言われる。 ・無視される、陰口や悪口を言われる。 ・業務をせかす、強い口調で言う。 ・責任や失敗を押し付ける。 ・人格、プライベート、容姿についてけなされる。 ・理由もない、事実でないことを報告されたり、告げ口のように噂を言う。 ・好き嫌いで仕事の時間や量の差別。 ・休暇や年休、妊娠等について不必要に非難されたり、理解されない。 |
これらの行為は、被害者のメンタルヘルスを損なうだけでなく、チーム全体の連携不足を引き起こし、最終的には患者ケアの質にも悪影響を及ぼしかねません。
ハラスメント被害に遭った時のための「自衛」策
もしパワハラの被害に遭ってしまったら、一人で抱え込まず、以下の行動をとることが重要です。
- 明確な意思表示: 「その言い方はやめてください」「そこまで言われたくないです」「つらいです」など、不快であることや行為を止めてほしいことを明確に伝えます。これにより、「相手が不快に感じていると知らなかった」という言い逃れを防げます。
- 信頼できる人への相談: 友人や家族、職場の信頼できる同僚、先輩に状況を話し、精神的なサポートを求めましょう。
- ハラメント相談窓口への相談:相談窓口の方は相談対応について学ばれていますので安心して相談することが出来ます。
- 証拠の収集: あまりにひどい時は「いつ、どこで、誰が、どのような発言・行為をしたか」を具体的にメモに残します。可能であれば、ICレコーダーでの録音や、メール、メッセージの保存も有効です。
一人で悩まない! ハラスメント外部機関の活用
職場内で解決が難しい場合は、外部の専門機関に相談しましょう
- 日本看護協会: 看護職のためのメンタルヘルスやハラスメント専門相談窓口があります。
- 労働条件相談「ほっとライン」: 厚生労働省による電話相談窓口です。ハラスメントについては専門の窓口を紹介してくれます。日本語に加え英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語、ミャンマー語、ネパール語、韓国語、タイ語、インドネシア語、カンボジア語(クメール語)及びモンゴル語の13言語に対応しています。
これらの機関は中立的な立場で話を聞き、適切なアドバイスや介入を行ってくれます。
チームで取り組む予防策
最も理想的なのは、パワハラが起こらない環境を構築することです。
- 院内研修の実施: 管理職や全職員を対象としたパワハラ防止研修を定期的に行い、パワハラの定義や影響について共通の認識を持つことが重要です。
- ハラスメント相談窓口の周知: 相談窓口の存在と利用方法を職員に周知徹底し、相談しやすい雰囲気を作ります。
- 風通しの良い職場文化: 役職や経験年数に関わらず、意見や疑問を言いやすい、お互いを尊重し合う文化を醸成することが、パワハラ防止の鍵となります。
看護師や医療従事者のパワーハラスメントが起きないための取り組み
ハートセラピーでは「チーム・ウェルビーング研修」というお互いを活かしあうチーム作り研修を通してパワーハラスメントをおこさない組織風土作りを支援しております。前向きな課題解決法である「解決志向」を学び追い詰めない指導法や考え方ができると、自分自身もストレスが少なくなります。また、スタッフ同士だけではなく患者指導にも大いに役立ちます。多くの病院で取り組み始めている「チーム・ウェルビーング研修」を導入しませんか
詳細は、お気軽に下記よりお問い合わせください。
まとめ
看護師のパワハラ問題は、個人の問題ではなく、組織全体で取り組むべき課題です。被害を未然に防ぎ、もし発生してしまった場合は適切に対処できるよう、私たち一人ひとりが意識を高めていく必要があります。
あなたの尊厳を守り、すべての看護師が心身ともに健康で、やりがいを持って働ける職場環境の実現を目指しましょう。
関連コラム