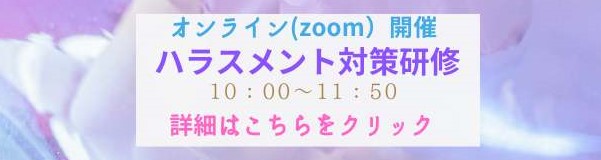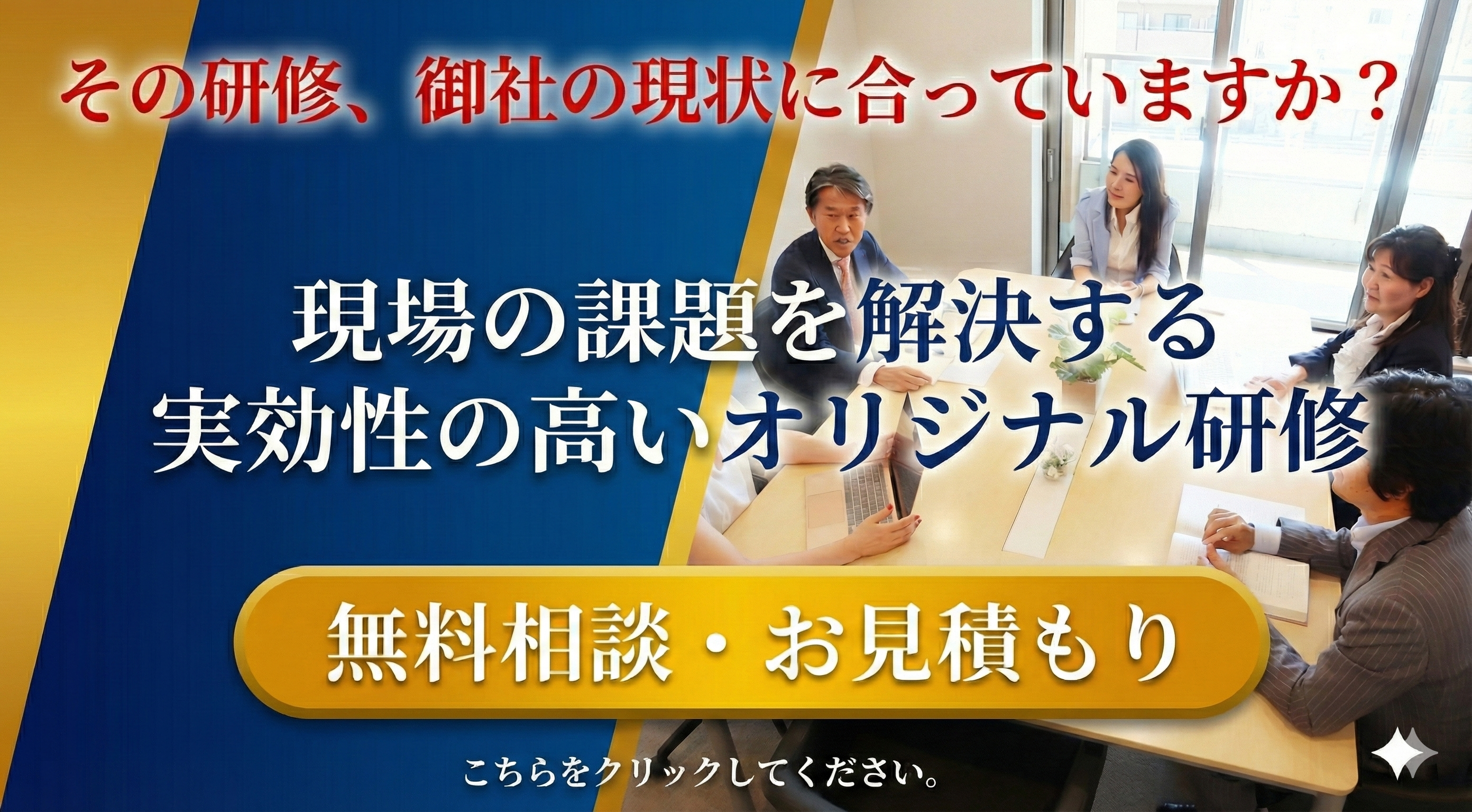パワーハラスメント対策と組織活性化を両立する「解決志向アプローチ」
目次
弊社の支援実績と確信
弊社は2008年の創業以来、企業、行政、大学、病院など、多岐にわたる組織に対し、ハラスメント対策の支援を提供してまいりました。経営層やご担当者様からのご相談に応じ、単なるハラスメント防止で終わらせず、社員が意欲的に働ける、生産性の高い組織づくりをサポートしています。
長年の経験から、パワーハラスメント対策に最も有効で、かつ組織の活性化に繋がる方法を確信しております。今回は、その「解決志向アプローチ」についてご紹介します。
パワハラ加害者の特徴:「問題志向」からの脱却
パワハラ加害者の特徴として、コミュニケーションが一方的であること、価値観の許容範囲が狭いことなどが挙げられますが、その一つに「問題志向」の考え方があります。
問題志向を持つ人は、他者の「足りていない点」や「できていない点」に目が向きやすく、許容範囲の狭さから、すぐにイライラして指摘をしてしまいます。
現在、アンガーマネジメント研修が広く普及していますが、私はそれよりも先に「解決志向アプローチ」の研修を受講されることを推奨します。なぜなら、これは「怒りをコントロールする」のではなく、「そもそも怒りを発生させない」ための考え方を学ぶことができるからです。

解決志向アプローチによる指導の重要ポイント
1. 些細な「資源」に着目する
解決志向アプローチでは、「少しでも」できていること、「少しでも」上手くいったことなど、小さな成功体験や能力(資源)に着目します。
例えば、カウンセリングで「できていることはありますか?」と尋ねても「ありません」と答えがちですが、「少しでもできていることはないでしょうか?」と「少し」という言葉を加えるだけで、ほとんどの方が何かしらの資源を答えてくださいます。さらに、一つ資源が見つかると、それを足掛かりに二つ、三つと、本人の「できていたこと」や「上手くいっていたこと」が掘り起こされていきます。
このように資源を掘り起こし、本人に気づかせることで、「自分は全然ダメなわけではない」と前向きな気持ちを引き出すことができます。また、「上手くいっていたとき、どのような状態でしたか?」と思い出してもらい、その成功要因を分析することで、「あのやり方でやればいいのだ」と自ら解決策に気づくことができます。
2. スモールステップで行動計画を立てる
できていない人に対し、いきなり「完全にできるようにしなさい」「いつもそのようにしなさい」と求めると、相手は困難を感じて行動できなかったり、一時的に行動できても継続できなかったりします。
解決志向では、スモールステップを大切にします。例えば、「0」が全くできていない状態、「10」が目指す姿だとした場合、現状の資源を挙げていただいて本人が「今は2点」と評価したとします。その場合は「では3点にするためには、何をすればよいか」と訊ねて、計画を立てていただきます。
ポイントは、「簡単に、すぐにできる行動計画」にすることです。相手がそれを実行できたとき、「上手くいきましたね」「ここまで進みましたね」と承認の言葉をかけます。これにより相手の自己肯定感が上がり、自発的に次の行動に移れるようになります。
やる気のなさそうな人や理解が遅い人の多くは「自己肯定感」が低いため諦めていることが多いのでちょっとしたきっかけで変わります。
これは家庭でも同じです。例えば、パートナーに完璧な掃除を求めるのは難しいですが、「少しでも部屋を片付けてくれようとした」「部分的に掃除機をかけた」という時点で「ありがとう」と伝えれば、相手は継続してくれます。「なんで片づけないの!いつも私ばかりで嫌だ!」という問題志向の伝え方では、対立を生むだけです。
職場での部下育成においても、いきなり高い目標を課すのではなく、スモールステップで計画を立て、承認しながら育成する方が、一見遠回りに見えて、実は最も近道です。大きな歯車も、わずかに動かせば、あとはスムーズに回り始めるイメージです。
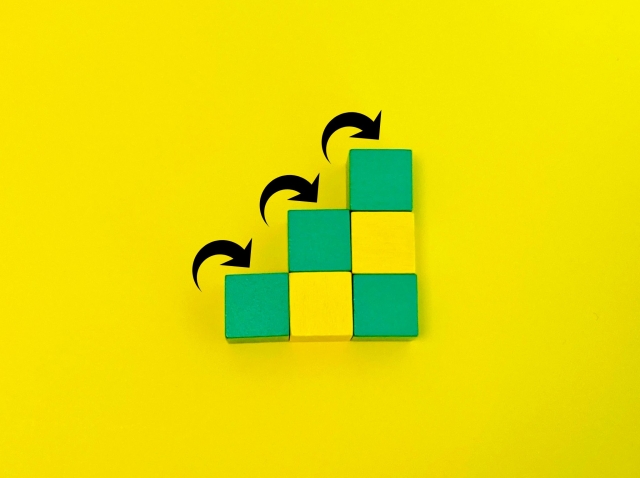
パワハラ対策としての解決志向の有効性
解決志向という前向きな課題解決法で指導すれば、相手を落ち込ませすぎたり、追い詰めてしまったりすることなく、自身の資源を活かしながら課題と向き合い、成長させることができます。
本コラムではここまでといたしますが、他のコラムでも解決志向についてご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
また、私が過去にハラスメント対策検討会の委員を務めていた際、人事院のご担当者様から「先生、パワハラ対策はこれですね」と太鼓判を押していただいた小冊子をご活用ください。短い漫画や挿絵を含み、パワハラの本質や解決志向について分かりやすくまとめてありますので、皆様のテキストとしてご活用いただければ幸いです。詳細についてはこちらをご覧ください。ご購入は下記バナーをクリック
【書籍】ハラスメントが起きない職場のつくり方